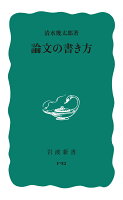ゼミや購読などの授業で、学生たちにレポートや論文の書き方を指導しています。
相手があることなので、思うようには進みません。
人文系の論文というものは多様な方法や類型が存在します。いくつかの決まった型、思うに随分昔から収斂されてきたような決まった形というものが存在しているようです。
そうした型に当てはめていくこと自体は単純作業なんですが、では、いざ書こうとすると最初の一歩がなかなか大変です。
自分の狭隘な知識をできるだけ広角レンズにしながら、頭の中の引き出しを開けては閉め、構想を練って、とにかく書き出していかなければ始まりません。
論文指導は大変

学生には、自分のテーマに関連して、なんでもいいからレポート形式で1枚、わが専攻では卒論を1600字が1ページになっているので、その形式で書いてごらんと言っています。
しかし、この「なんでもいいから」が曲者です。
我ながらもっと細かく指示すべきだろうと心では思うのですが、最初の一歩があれば、それを材料にして、レポートを膨らませることも、次のレポートのテーマが浮かんでくることもあります。
まずは「なんでも」を考えてもらわねば埒があかないのです。しかし、いくつかの発想を、示唆していってあげないといけません。
『論文の書き方』(清水幾太郎著 岩波新書)の概要

清水氏は著名な社会学者であり、論文、文章を書く名手でもあります。
この本は氏の学生時代、教員時代の経験を踏まえて書かれています。
どうすれば、すんなり理解できる文章が書けるのか、氏は、短文の600字や1000字という決まった枠の中で、連載していったことが文章を書く鍛錬になったと言っています。やはりそうなんですよね、と納得するしました。
ある学術書を読み、その内容について書評を書きます。その積み重ねが経験になります。書物の内容を批判的思考で理解し、咀嚼し、短い文章にまとめなければならないのです。
筆者は、数百ページある著書を相当な部分削りながら、核心は外さないようにする、そのスキルが求められるといっています。それを習得するためには、日々書くことの習慣が大切だということです。
さらに新聞記事の文章を参考にしない方がよいといっています。
私たちは今まで学生に新聞の5W1Hの事実の書き方を参考にし、わかりやすい文章を書きなさいと指導してきましたが、まるっきり逆です。
新聞は確かに確実に事実を伝えるには大変参考になります。しかし、清水氏は新聞には「が」が多いといいます。「が」はセンテンスを繋ぐには便利であるが、本来は多様な接続詞に置き換えられるものであり、その方が正確な意味となるのだそうです。
また、文章は空間の時間化ともいいます。
見たままの空間を時間の中で組み立てなおすのです。見たまま、あるがままではないのです。
さらに経験と抽象の往復ともいいます。
経験したことは、事実として書きやすいです。しかしその経験にはなにがしかの意味があるし、背景もあるし、いわゆる抽象的な観念を属性として持っているのです。
日本語は英語と違い、最後に動詞が来ます。主語がない場合も多いです。
したがって、文章の結末が最後で分かるため、文章の終わりまで何がどうしたかを記憶しておく必要があります。
そのため、特に日本語のこうした構成を考えたとき、氏の言葉を借りれば「複雑な内容を正しく表現しようとすればするほど、一つ一つの文章は短くして、これをキッチリ積み重ねて行かねばならない」のです。
これから文章を書こうという学生には、論文の構成や体裁だけではなく、どれだけ読み手に伝えることができる文章が書けるかという点で、ぜひ読んでほしい一冊です。
『論文の書き方』 の書誌情報と参考文献
『論文の書き方』(岩波新書F92)清水幾太郎著 岩波書店 1959年
この本の他、定番となっている論文の書き方の本が以下の2冊です。
『シカゴ・スタイル研究論文執筆マニュアル』
ケイト・L・トゥラビアン 著, ウェイン・C・ブース, グレゴリー・G・コロンブ, ジョセフ・M・ウィリアムズ, シカゴ大学出版局エディトリアル・スタッフ 改訂, 沼口隆, 沼口好雄 訳
慶應義塾大学出版会, 2012.11
ISBN 978-4-7664-1977-1
『APA論文作成マニュアル』 第2版 アメリカ心理学会 (APA) 著, 前田樹海, 江藤裕之, 田中建彦 訳
医学書院, 2011.3
ISBN 978-4-260-33354-2
参照文献の書き方は、SIST-02を基本としています。