小説「図書館戦争シリーズ」に描かれた事件にはモデルとなった実際の事件があります。
それを探ってみましょう。
有川浩著「図書館戦争」シリーズ
図書館戦争シリーズは、人気作家の有川浩の著作として、ライトノベル系の出版形態をとりながら、言論の自由及び図書館の自由についての論考を提示しています。
そして、物語性としても、冒険性や恋愛を織り交ぜ、そこに、組織のかけひきなども興味深く展開されているベストセラー小説です。
この小説で描かれたモチーフは恋愛ですが、構成全体の背景にあるのが、「図書館の自由」です。
フィクションである小説に描かれた内容を鏡にして、現実の問題を抱えた図書館を映しだてみましょう。
小説と現実を対比してみるとこうなります。
時代設定と社会的背景
小説における時代は「正化三十一年」、昭和最終年から30年後という設定です。
昭和最終年に「メディア良化法」が施行されて30年ということになっています。
メディア良化法とは、公序良俗に反するメディアに対して、検閲を実施できる法律です。
もちろん、現実には、こうした直接的な検閲法はありません。
メディア良化法に基づき、それを実際に執行する組織が、「メディア良化委員会」です。その代執行組織が「良化特務機関」となっています。
物語は、この検閲機関である「良化特務機関」とそれに対抗するべく成立した図書館法第4章(「図書館の自由に関する宣言」を法制化したもの)を盾に持つ広域地方行政機関の「図書隊」との対立構造で展開し、図書隊の検閲への闘いが描かれていきます。
現実は、検閲によって出版できない事例とは本質的に全く違ますが、現行法に抵触する、例えば著作権侵害や、プライバシー侵害の提訴により、出版の差し止め命令ということで、判決が出るまで争われ、それまで出版できないケースは起こり得ることです。
柳美里著の『石に泳ぐ魚』の問題もその一つでしょう。
しかしそうした訴訟は、出版社に対するものですので、判決の内容が図書館の蔵書に及ぶわけではありません。
もし図書館の蔵書が対象となれば、所蔵している図書館全部を訴える必要があるわけです。
しかしながら、公共的立場として、判決の趣旨を考慮しないということもできないのです。そこが、難しいところです。
公共図書館でも、図書館組織内部を含めたその他関係部局、例えば人権部局からの資料の問題表現に対する指摘などは十分あり得ることです。
図書館の主体的な考え方が問われるケースや図書館資料の取り扱い方法について、検討し、結論を出さなければならない事例は現実的に発生しています。
検閲の方法と抵抗権の執行
小説では、事前検閲が、出版流通の過程で、義務付けられた見本誌と出版データの提出により、取次協会内のメディア良化委員会分室内で執行さます。
しかし、いくらフィクションとはいえ、膨大な出版物の事前検閲は物理的に無理なため、実際は出版後の指摘により取締りが行われるという状況が大半であるとされています。
事前検閲がザル状態であること自体が、小説では、図書館所蔵資料の価値を高めているとも言えます。
通常の出版流通過程における検閲、いわゆる出版差し止め、回収にいたる場合であっても、図書館の蔵書については言及されません。
小説において、それは図書館法に依拠しているためなのです。
設定では、図書館法は、メディア良化法に対して唯一の抵抗権を持った法律となっています。
たとえば、見計らい権を行使して、書店の検閲回収資料を見計らい資料として検閲権の及ばない資料とできるような権限があります。
もちろん図書館の蔵書となると全く検閲の及ばない資料となります。
では現実ではどうかと考えたときに、小説の図書館法に規定された図書館の自由は一定の効力がありますが、実際の「図書館の自由に関する宣言」は、図書館の根幹となる知る自由、資料提供の自由などを保障する理念が明文化されたものであり、裏付けとなる憲法以下、各種法的根拠はあっても、強制力はありません。
組織の相違
小説では、各地方自治体に所属する図書館に対して、広域地方行政機関としての「図書隊」が存在します。
図書隊の組織構成は、人事等を担当する総務部、通常の図書館業務を行う業務部、防衛業務を行う防衛部、その防衛部の中に、タスクフォースとして図書特殊部隊があるという、武力を持った強力な防衛組織となっています。さらに、アウトソーシングされた後方支援部もあります。
小説では、日本図書館協会も存在し、「未来企画」という研究会もあります。
図書隊内には派閥があります。
それは、メディア良化委員会寄りである行政派と「図書館法第4章」を理念とする原則派でです。
そこに、「未来企画」のメンバーが絡み合うこととなります。
現実の公共図書館は言うまでもなく、各地方自治体の教育委員会に属していますが、最近では首長部局に移った図書館も存在します。
また、NPO団体等が運営主体となる指定管理者による運営も増えてきているます。
その場合、運営について管理監督する部局は教育委員会になります。
臨時職員の割合が増してきた現在においては、その臨時職員でさえ人員確保が難しい状況が増してきています。
いわゆる正規職員採用が減ってきて、そうした絶対的な人員確保が難しい状況下で、今まで図書館職員がやっていた業務を委託に移行しつつある自治体も増えてきています。
フィクションの中のメタファー
小説はフィクションであるため、例えば、法体系にしても検閲を許可した法律と、それに対抗できる法律の、相矛盾する法体系が存在します。
現実には、そうした法的矛盾はありえないことですが、検閲を許してしまう法律が成立する背景には、国民の無関心さに起因しているように描かれています。
そのことは現在の世相にも置き換えられる警告を含んでいるのではないでしょうか。
対立した組織を描くことで、ドラマ性を引き立たせ、強調されたモチーフから、現在の図書館が抱える自由の問題を批判的に解釈していけると考えます。
また、図書館組織や研究会を絡めた内部派閥の対立構造も、現実の図書館内部や関係部局との関係を比喩的に見ることができます。そうした構成力が、このベストセラー小説の興味深いところなのです。
図書館の自由に関する事例
小説での事件と、そのモデルとなった実際の事件を見ていきましょう。
「望ましくない図書」隠蔽事件
館内整理後間もない時期に、不明図書が14冊発生したという事件が描かれています。
タイトルは「望ましくない図書」に指定されていた図書ばかりであったため、挙動不審な行政派の鳥羽館長代理による隠蔽が推測されました。
そのため、図書特殊部隊から、注意喚起の通知が流され、ひそかに不明図書が発見されるということでとりあえずの収拾がついたという事件でした。
現実を見てみましょう。
古いところでは、1979年の「図書館の自由に関する宣言」の改定のきっかけにもなった山口県立図書館での反戦・左翼系の図書をダンボールに詰め書庫に放置した事件があります。
この事件後の1979年の「図書館の自由に関する宣言」改定で、「図書館は利用者の秘密を守る。」が新しい第3宣言として加えられました。そして、3番目が4番目になり、「すべての不当な検閲に」が「すべての検閲に」になりました。つまり正当な検閲などないということです。
また、2001年には特定著者とそれに関係する図書のみを廃棄した事件として、船橋市西図書館蔵書破棄事件があります。
高校生による連続通り魔殺人事件における未成年者の読書記録
小説では、捜査令状なしで捜査協力ということで描かれています。
この際、未成年であることとは切り離して考えるべき論点となります。
また、ストーリーを展開するにあたって、メディア良化法施行後、一定期間の貸出記録を残しておくことが義務付けられていることとなっています。
小説では、稲嶺司令が警察への協力は全面的に拒否しています。
しかし、それに至るまでには、行政派の館長代理により偏向的なアンケートが実施されているのです。
現実には、裁判所の捜査令状による場合、利用者の読書記録開示が行われることになりますが、実際的には、ほとんどの図書館では、過去の貸出記録は残らない(コンピュータに一定期間のログは残りますので、それが消えていなければわかります。)ため、現在の貸出中の記録しか開示できないことになります。
しかし、開示は裁判所の正式な捜査令状による捜査の時のみです。
図書館は、現状、司法の判断に従うということになります。
しかし、それはあくまでも司法による命令が図書館に直接的な場合に限ってのことであり、前述したような、例えば、図書館資料に言及しない場合などは、その限りではありません。
「子供の健全な育成を考える会」による事例
小説での事件は、教育問題を盾にし、学校図書館及び公共図書館の蔵書のうち、青少年に有害とその会が判断したものについて、蔵書から排除していくという組織の活動が描かれます。
それに対して、反対する中学生が、その会合に、度が過ぎた抗議行動を起こし、図書隊に捕まるという展開があります。
図書隊は「あらゆる不当な検閲に反対する」理念の下、少年の考えを、「子供の健全な育成を考える会」に対して、マスコミを巻き込んで、少年の考えに同調し主張していきます。
図書隊の策としてはマスコミで取り上げてもらうことにより、世論に訴えかけ、蔵書の排除をやめさせるというものです。
現実には「青少年保護育成条例」による有害図書指定などがあります。
しかし、ここで対象となる図書とは、いわゆる一般的な出版流通ではない、アダルト系の本やビデオであり、それ以外の出版物がその対象になることはほとんどありません。
近年では岡山市が指定した「完全自殺マニュアル」や「ザ殺人術」がその例外にあたると考えられますが、この例外について、公共図書館において利用制限を設けることの是非については、検討の余地があるでしょう。
その自治体が有害図書に指定しても他の自治た判断ではそうしなかった場合、相互貸借で、他市から借りてくることもできるはずです。
指定を受けていない他の自治体では閲覧できるという矛盾もあります。
有害図書指定の趣旨と、図書館資料としての機能的側面を同じ土俵の上で議論できるか否かを別にして、行政内部等から図書館としての対応及び説明を課せられることは往々にして起こりうることです。
批判的書評を図書館のHPに載せた事例
小説で描かれた、一図書館員による「一刀両断レヴュー」は、特定の図書の内容を誹謗中傷する内容でした。
それは、当然のことながら、この小説でも図書隊の主要メンバーが疑問に思い、削除を望んだものです。
物語は予想に違わず、出版社から強い抗議、そして和解へと展開します。
現実には、図書館の本の紹介は、書評ではないと考えます。
内容の一部紹介と客観的な事実が主な内容として掲載されるものです。
したがって、図書館の本の紹介は、さまざまなバイアスのかかった私的なブログやマスメディア、書店の運営する書評コーナーとは明らかに性格の違うものであるのではないでしょうか。
「床屋」という言葉に対する自主規制強要事例
小説では、タレントの生い立ちを週刊誌が取材する課程で、タレント自身が、祖父の仕事への愛着もこめて「床屋」という表現を使います。
この床屋という表現が、「メディア良化委員会」に指摘を受けるのではないかということで、編集段階で、「理容業」という言葉に、差し替えようとします。
しかし、その言葉を使ったタレント自身が、その差別性を否定し、むしろ勝手に言葉を差し替えようとしたことに怒り出します。
しかし、図書隊の上司と出版社の編集者がタレントに、問題の根源が、「メディア良化委員会」にあることを、理解してもらい、逆に、タレントが出版社側をわざと訴えることにより、世論の支持を得て、検閲に一石を投じようと図るのです。
現実にこうしたケースでは、図書館が介入することもないのですが、「床屋」に差別性があるかないかの議論は別にして、メディアの自主的な規制というものは存在します。
特に映像メディアでは、音声を消したり、最初に断り書きを流したりしています。
原作では、著作人格権上、削除できないため、奥付の前頁に断り書きを付すこともあります。
特に文庫化に当たっては、ほとんどこの断り書きで対応しています。
図書館で問題になった場合であっても、特に訴訟で公判が終了している場合や、出版社から改訂版が出ない限り、言葉のみの差別性を認識しても、利用制限することはありません。
小説における茨城県展の事例
小説では、茨城県展で最優秀賞を取った「良化特務機関」を批判する絵画「自由」をめぐっての、良化特務機関と図書特殊部隊との攻防戦が描かれます。
これは、昭和天皇の肖像を使った版画「遠近を抱えて」の一連の富山県立近代美術館における「不敬」問題に関わっての作品廃棄、非公開問題、県立図書館における図録受け取り拒否による係争問題が現実の事件と空いてありましたので、それがモデルとなっています。
この問題は、市民らの訴訟を受けて、富山地裁は、美術館行政の誤りを正し、原告一部勝訴の判決を下しています。
しかし、図書館の図録問題では、図書館の判断の正当性が認められ、いまだに封印されたままとなっています。
原発テロ事件のモデルとなった小説の著者に対する言論封鎖事例
小説では、原発テロ事件のモデルとなった小説の著者の著作活動に制限を加えようとするのですが、図書特殊部隊は、この著者を極秘裏に保護し、最終的には日本国内では法的に活動できなくなる現況で、亡命という方法を選択します。
そこに行政内部にも繋がりを持つ「未来企画」と取引をし、マスコミを利用して、言論の自由の危機的状況を国民に対して訴えかけようとします。
そして、政府への働きかけを「未来企画」を利用して企てます。
その結果、世論の後押しから、著者の著作活動が保証されることとなるというものです。
過去に、小説が犯罪のモデルとなったこともありますが、その著者が拘束されたりすることは、日本国内で、現実にはありません。
小説はフィクションであって、現実には、それをもって著作活動を制限することは、表現の自由の侵害となってしまいます。
まとめ
図書館と自由を取り扱った小説はこのシリーズが初めてで、有川浩が、図書館の事例の文献を調査していることがうかがえます。
改めて、モデルとなった事例を認識して読んでみると、新たな問題点が見えてくるのではないでしょうか。
書誌情報
小説は、現在、角川書店の文庫版が出版されています。
『図書館戦争』 2011年4月 ISBN978-4-04-389805-3
『図書館内乱』 2011年4月 ISBN978-4-04-389806-0
『図書館危機』 2011年5月 ISBN978-4-04-389807-7
『図書館革命』 2011年6月 ISBN978-4-04-389808-4
『別冊図書館戦争I』 2011年7月 ISBN978-4-04-389809-1
『別冊図書館戦争II』 2011年8月 ISBN978-4-04-389810-7

図書館戦争 LOVE&WAR コミック 1-15巻セット (花とゆめCOMICS) Amazonで購入

図書館戦争シリーズ 文庫 全6巻完結セット (角川文庫) Amazonで購入

図書館戦争 THE LAST MISSION プレミアムBOX [Blu-ray] Amazonで購入
図書館の自由に関する宣言
図書館の自由に関する宣言(抄)
図書館は、基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、資料と施設を提供することを、もっとも重要な任務とする。この任務を果たすため、図書館は次のことを確認し実践する。
第1 図書館は資料収集の自由を有する。
第2 図書館は資料提供の自由を有する。
第3 図書館は利用者の秘密を守る。
第4 図書館はすべての検閲に反対する。
図書館の自由が侵されるとき、われわれは団結して、あくまで自由を守る。
「図書館の自由に関する宣言」全文は、日本図書館協会のホームページにあります。
<参考文献>
「図書館とメディアの本 図書館のコスト/船橋西図書館の蔵書廃棄事件」『ず・ぼん』 11 ポット出版 2005
「図書館とメディアの本 岡田健蔵の函館図書館/スペシャルインタビュー有川浩」『ず・ぼん』 13 ポット出版 2007
東条 文規『図書館の近代 私論・図書館はこうして大きくなった』ポット出版 1999
アメリカ図書館協会知的自由部『図書館の原則 図書館における知的自由マニュアル』(第7版) 日本図書館協会 2007
日本図書館協会図書館の自由に関する調査委 『表現の自由と「図書館の自由」』(図書館と自由) 日本図書館協会 2000




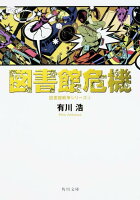
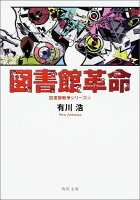
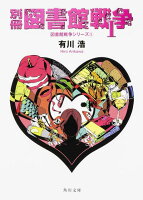
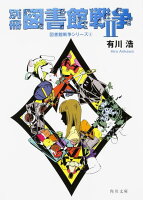
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/209081c5.595cf197.209081c6.1208da3b/?me_id=1213310&item_id=17751089&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9527%2F4988111149527.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


