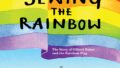情報とメディアという言葉は、よく聞いたことがあると思います。
いったい情報って何だろうとか、メディアって何だろうということをあまり深く考えずに、使っていることが多いのではないでしょうか。
情報とメディアについて、詳しく見ていきましょう。
情報とは何か

情報ってどういうものなんですか。

情報はみんなの生活の中の至る所にあります。今、目の前にあるもの、感じたものなんかも情報といえるものじゃないかな。

じゃあ、情報の定義から見ていきましょう。
情報の定義
JISによる定義は、「事業、事象、事物、課程、着想などの対象物に関して知り得たことであって、概念を含み、一定の文脈中で特定の意味を持つもの」となっています。
つまり、情報とは、物事について知ることであり、何らかの意味を持っていて、受け取った人に何らかの判断材料となるものといったところでしょうか。
ということは、逆に言うと、判断材料として意味を持たないものは情報ではないということですね。
情報はものとは違う
お菓子を人にあげたら、自分の手元にお菓子はなくなりますが、情報は複製されて、送り手も受け手も残ります。つまり、複製できるのが情報ということです。
グーテンベルクの活版印刷の発明で、情報が複製される量が爆発的に増えました。さらに現代では、インターネットが普及し、デジタル情報が複製されて拡散していきます。量もスピードも全然アナログな時代とは違ってきています。
情報の特性
情報の残存性:一度作られた情報は。消えることがありません。
情報の複製性:情報は簡単に複製できます。デジタルだととくに、複製しても劣化しません。
情報の伝播性:情報は、いったん外部に出ると、拡散していく傾向にあります。特にインターネットの普及により、この伝播性は、より広い範囲に、迅速に伝わるようになってきました。
メディアとは何か

メディアと一口で言っても、多様な意味を持っています。
メディアをカテゴリー化すると、次の3つになります。
表現のためのメディア
表現のメディアとは、私たちが情報をどのようにして表すのかということです。たとえば、文字、音声、動画、静止画などの表現方法を用いると思います。また、文字を音声に変えたり、表現のメディアでは、違う表現に変えるということもよく行われています。
表現のメディアの種類:文字・音楽・音声・表・図・写真・動画・映像など
伝達のためのメディア
伝達のためのメディアとは、私たちが情報を何によって知るのかということです。たとえば、誰かからの手紙、電話、毎朝見る新聞、テレビ、スマホやパソコンはインターネットですよね。
そのほかにも、誰かが来て手渡されたメモ書き、掲示板、運転していれば、標識や信号などです。
伝達のメディアの特徴

記録のためのメディア
情報の記録や伝達のために使われるものが、伝達のためのメディアです。
アナログなものとして、メモ用紙や、手帳、ノートなどがありますが、これらは紙とも限りません。デジタルで、そういうアプリも存在します。
また、まったくデジタルな媒体として、CD-ROM、ハードディスク、USBメモリ、SDカードなど、様々な形式のファイルを保存することができます。
技術の進化と情報の進化
高度情報ネットワーク社会において、正確な情報を得ることと、それを活用する能力は、複雑な社会を生きていくうえで、欠くことのできないスキルとなってきます。会議でプレゼンをする、デジタルで家計管理をする、E-taxで確定申告をする、助成金を受けるなど、さまざまな状況でわれわれは情報を的確に把握する必要があります。
また、把握するだけではなく、情報を解釈し、自分なりの考えを導き出す必要もあります。
現代社会においては、インターネットの普及により、情報を得やすくなっています。またその情報を利用して、今までは参加しにくかったことに、参加できるようにもなってきています。
日本という資本主義社会においても、その資本の運用に参加しやすくなってきています。
時代の進化は、絶えず技術革新というイノベーションによって、経済活動は伸展していっています。そこに誰でもが参加できる世界となっています。
しかし、同時に多様な格差も広がっており、その経済成長の恩恵を受けるためには、インターネットを使える環境を持っている必要があります。こうした、現代社会の抱えるデジタルデバイドの問題の緩和は、お金がなくても情報インフラを使える環境が必須の要件となります。
そして、誰でもが、情報リテラシーを身に着け、生きる力を涵養することが望まれます。