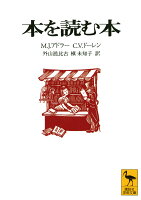読書には段階的なレベルがあります。そのレベルを高めていくことで、読書の本来の在り方が見えてきます。
そうした基本的な読書の方法について私たちは義務教育の中で教えてもらったことがあるでしょうか。
小学校の3年で同じクラスになった子に、ものすごい読書家の子がいたのですが、おそらくそのような子は自分で読書の方法を知らず知らずに覚えていったのでしょう。
どこかの時点で習ったことのある熟読、精読などという概念は記憶にありますが、それ以上でもそれ以下でもなかったように思います。
また、高等教育の中で、自分がいろんな本と出合っていく中で、読書の実践的ハウツーは載っていました。
しかし、この『本を読む本』のように、最も基本的なことを踏まえながら、高いレベルまで説得力を持って説明されたものはなかったように思います。
著者について
著者の一人、M.J.アドラーは、シカゴ大哲学教授、哲学研究所所長、エンサイクロペディア・ブリタニカの編集長を歴任、C.V.ドーレンは、エンサイクロペディア・ブリタニカ・インコーポレイテッド副社長です。
二人とも権威ある百科事典に中心的に関わった人たちでした。
事典編纂とは、事項や言葉の定義を、その時の定説や、それ以外の論も踏まえて、限られた文字数の範囲で正確に記述していかなければなりません。
それだけに地道で膨大な労力と時間が伴います。
実際の項目の執筆はその時の権威のある第一人者であることが多いです。それを、特に編集長であったアドラーは、責任者としてまとめていかなければならない立場にあったと考えられます。
読書の四段階のレベル
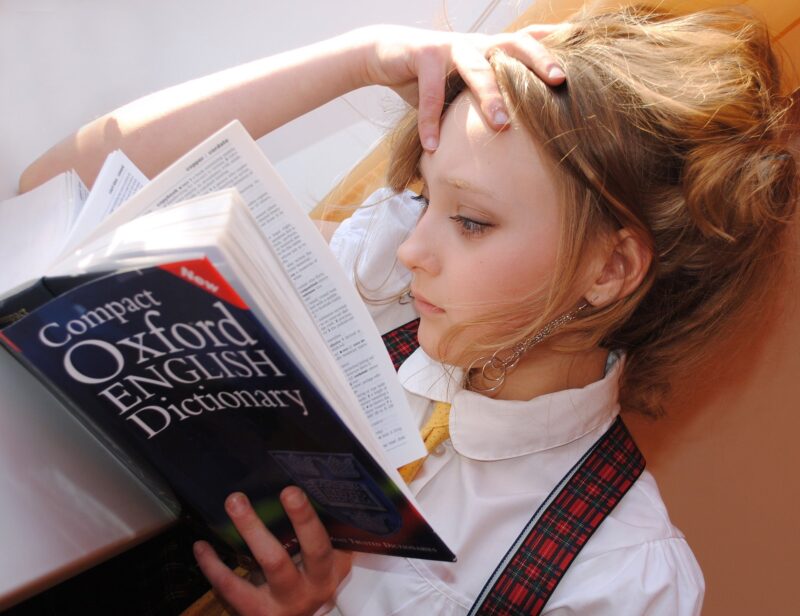
著者は、読書のレベルを四段階に分けています。
第一レベルは初級読書です。
これは、単語の意味を知る段階といえます。
第二レベルは点検読書です。
これは、その本にはどんなことが書かれているか、概要をつかむことです。
地図を予習しておいて、全く知らないところを旅する方が、迷わなくて済みます。しかしこのことを意識している読者が意外と少ないのです。
いよいよここからが本番です。
第三レベルは分析読書です。
本に書いてあることは著者の言葉であり、専門分野も著者の専門分野であり、専門用語であります。
文章は著者の理解のもとに展開しています。
そのため、著者とは違う読者の知識と折り合いをつけて、理解する必要があります。
そして、正しく批判する批判的読書へと進む。正しくとは根拠をもって批判しなければならないということです。
ここで、著者は文学書と教養書の読書の違いについて示しています。
「フィクションは主として想像力に訴える。」とし、「文学の影響力に抵抗してはならない」としています。心に働きかけるため、積極的な受け身であるということです。
さて、読書の最終目標、第4レベルはシントピカル読書です。
同じ主題について2冊以上の本を読み、その論点の違いについて分析することとしています。
同一主題のものを見つけ、論点の違いを中心に比較しなければなりません。これが意外と難しい。この方法を五段階に分けています。
実践していること
この『本を読む本』を読んでから、特に目次読みは必ずやっています。
そして、批判的読書としても、できるだけ、同一主題の本を複数読まなければと思うのですが、限られた時間で、やはり一冊で満足してしまう傾向は強いです。
しかし、それをやって初めて本当の読書の醍醐味があると考えます。
書誌情報
『本を読む本』(講談社学術文庫) M.J.アドラー,C.V.ドーレン 著 外山滋比古,槇未知子 訳 講談社 1997年
ISBN 978-4061592995