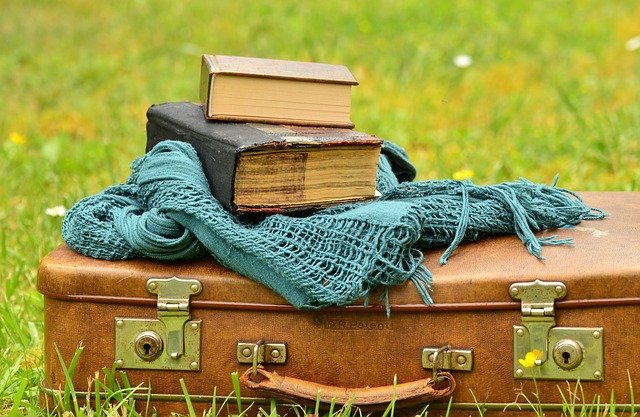最近、古書の世界ってどうなっているのか、興味がそちらに向いてしまっています。
大学の図書館で古書のあたり(NDCの分類でいうと024あたり)を見ていると、『本を愛しすぎた男』というタイトルが面白そうだし、実話のルポみたいなので借りてみました。
『本を愛しすぎた男』 ってどんな内容?
副題に「本泥棒と古書店探偵」とあるので、いろんな古書の盗難事件を追っているのかと思いきや、一人の泥棒と、古書店組合のABAA(アメリカ古書店協会)の防犯対策室長の対決のという構図でした。
著者は、ニューヨークタイムズやワシントンポストなどに寄稿しているライターです。
そもそも、著者に古書蒐集の趣味はなく、なぜこの取材をしようと考えたかは、400年前の一冊の古い本『薬草図鑑』が手元にあったことに始まります。
この本は人から譲り受けたものでしたが、どこかの大学図書館の蔵書印があり、どういういきさつで流出しているのかは不明でした。そこから、古書の盗難に興味を持った著者が、ある一人の泥棒を追って、取材したということです。
本泥棒の名前は、ジョン・ギルキー、古書探偵(ビブリオディック)の名前が、ケン・サンダースです。
詐欺師も同じようかもしれないのですが、ギルキーも礼儀正しく、身なりは清潔で、ある種、知性的なところがある人物です。
彼は何度か刑務所暮らしを経験し、仮釈放から、逃走してしまったり、また刑務所に収監されたりを繰り返しています。
さらに彼は、郡や州をまたいで犯罪を犯しています。古書窃盗は5年の時効がありますが、彼が、郡や州をまたいで、所轄の警察が変わることで捕まりにくくあえてしているのか、事項自体を知っているのかというと、そうでもないようです。
手口としては、他人のクレジットカード番号を入手し、古書店に電話で、注文して、別の人が取りに行くので、カードを持っていないから、あらかじめ店にカード会社へ支払いOKか問い合わせてもらい、それで支払いして、部屋だけ取ってあるホテルに送ってもらい、そのホテルに取りに行くというものです。おそらく現在では通用しない手口です。
彼にとっては、只で稀覯本の蒐集ができて、それを人に見せたいという欲求だけで行動しているようなところがあります(ただ、人に見せるという欲求を満たすことは現実にはできないのですが)。そして、それを邪魔されると、邪魔した方が悪く、復讐として再び古書の窃盗を犯すのです。まったく、身勝手な本泥棒なのですが、その考え方は、何度収監されても変わることがありませんでした。
この本のルポでは、本泥棒の窃盗を繰り返す原因は究明されていません。ただ、裕福な人だけが文化遺産を独占することが許せないのか、自分こそが古書蒐集家にふさわしいと自負しているのだろうか、そういうことが感じられました。
一方のサンダースは、古書店仲間とタッグを組んで、このクレジットカード詐欺の手法で古書店に注文してくる人物を特定し、送付先のホテルで待ち構えてギルキーを捕まえるということに成功します。
サンダースもギルキーも古書蒐集というコレクターとしては共通したところがあるのですが、手に入れる手法が、悪魔と天使ほど違うというものです。
最後に著者は、ギルキーから恐らく窃盗であろう別件の事実を聞くことになりますが、そこで、その事実を警察に通報すべきかどうかで心の葛藤があります。結局著者は、取材のそれを本にすることもできなくなるリスクがあるため、ネタ元の秘密は通報しません。
図書館で本がなくなること

ある時に気が付いたのが、書庫で保存していた『冷泉家時雨亭叢書』がところどころなくなってしまったことや、『上田秋成全集』『荷風全集』なども同じく数冊なくなっていました。これは図書館にブックディテクションシステムが設置される以前のことです。
別の大学図書館でこんな事件もありました。「被告は昨年9月〜今年2月、神戸市東灘区の神戸大付属図書館海事科学分館と、灘区の付属図書館総合・国際文化学図書館から、江戸時代に出版された讃岐國(さぬきのくに)名勝圖會(めいしょうずかい)(35万円相当)など古書計76冊(計210万円相当)を盗んだ疑い。」(2009.10.21「古書76冊窃盗 被告を再逮捕=兵庫」読売新聞 大阪朝刊 神戸 33頁)
本は、どんな本であろうが文化的な財産です。図書館の本を無断で持ち出し、個人のものとしてしまうと、他の市民は全くその文化的財産に触れることができなくなってしまいます。
また、切り取りや、本そのものを破壊するような人もいますが、これも同等の行為なので、許せません。
ブックディテクションシステムは、今では普通に図書館に設置されていますが、当初は、「市民を信用していない」とか「誤作動が」とかが、懸念されていましたが、損害額を見れば、もうその次元の話ではないということなのですね。
ネット通販の洋書が届いたら、図書館の本だった。
ネット通販で洋書を注文して、海外から発送ということをよくやりますが、その中に、この本の著者と同じように、図書館の本が届いたことがあります。これもどういう処理がされているのか全く分かりませんので、僕の蔵書の一部になっています。
日本だと、廃棄処理した本を市民にお譲りしますという「リサイクルフェア」(常設している図書館もあります。本来の意味からいくとリユースかもしれません。)のような催しを図書館で開催することがありますが、その時には、必ずバーコードを隠すように上から「リサイクル図書」という、粘着力の強いシールを貼るのですが・・・。
ネット通販で、図書館の本が届いた時には、司書としては複雑な気持ちで、心が痛みます。
『本を愛しすぎた男 』 の書誌情報
『本を愛しすぎた男 : 本泥棒と古書店探偵と愛書狂』 アリソン・フーヴァー・バートレット 著 , 築地誠子 訳 原書房 2013.11 978-4-562-04969-1